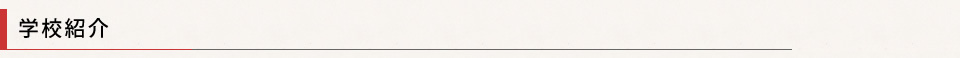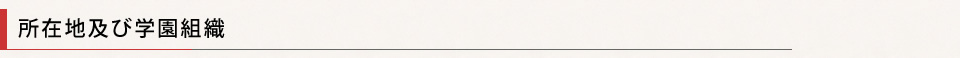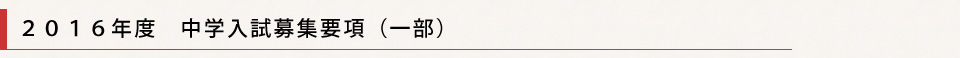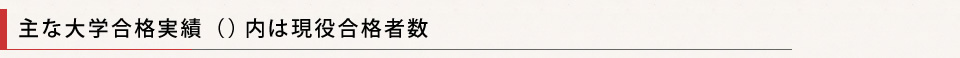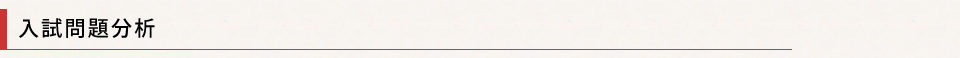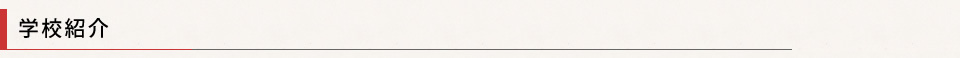
1872年(明治5年)、メール・セン・マチルドが創設した孤児院と寄宿舎が起源。1875年(明治8年)東京築地に築地語学校を開設。その後、1909年(明治42年)、雙葉高等女学校を開校。
「徳においては純真に 義務においては堅実に」の校訓のもと、生徒たちひとり一人の個性に目を向けたきめ細やかな教育をおこなっている。
雙葉生ま特徴は「場の空気をしっかり読み」「他者とのコミュニケーションに長けている」人が多い。
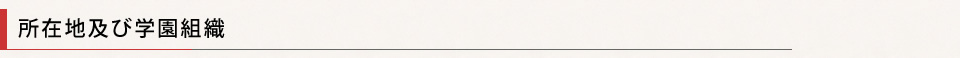
| ●所在地 |
〒102-8470 東京都千代田区六番町14-1 |
| ●交通 |
JR中央線・総武線、東京メトロ丸ノ内線・南北線「四ツ谷駅」より徒歩2分 |
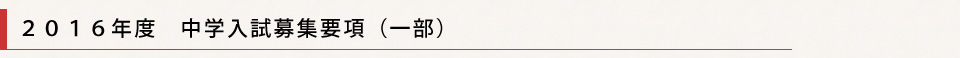
| ●募集定員 |
女子100名 |
| ●選抜方法 |
算数・国語・理科・社会、面接(本人のみ)、通知表コピーまたは報告書
※親元から通学するとともに、通学時間1時間30分以内が受験資格となっている。 |
| ●入試日 |
2月1日 |
| ●合格発表 |
2月2日9:00~ |
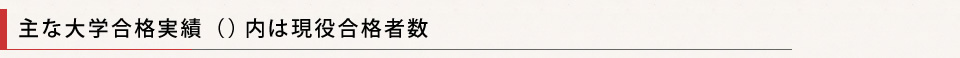
東京大学12名(9名)、京都大学5名(3名)、一橋大学6名(6名)、早稲田大学102名(88名)、 慶應義塾大学56名(49名)、
上智大学54名(48名)
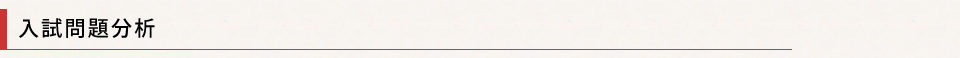 国語
国語
| 大問内容 |
| 大問1 |
随筆文(森下典子『日日是好日』) |
大問6 |
|
大問11 |
|
| 大問2 |
俳句と解説文(好本惠『俳句とめぐりあう幸せ』) |
大問7 |
|
大問12 |
|
| 大問3 |
|
大問8 |
|
大問13 |
|
| 大問4 |
|
大問9 |
|
大問14 |
|
| 大問5 |
|
大問10 |
|
大問15 |
|
| 問題解析 |
| 大問1は「お茶」の良さを「時間の流れの中で自身の成長を実感させてくれるもの」とし、映画の例などと重ね合わせている文章。比喩表現の具体化を求める設問が多く出題されました。大問2は雙葉では大変珍しい「俳句」を扱った文章で驚いた受験生も多かったのではないでしょうか。ただ、俳句の知識そのものを試す問題は少なく、一つの「説明文」と考えることが大切です。いずれにせよ、過去問の傾向を鵜呑みにせず、日頃から幅広い分野の学習に取り組むことが必要です。 |
算数
| 大問内容 |
| 大問1 |
計算・割合・速さ・食塩水 |
大問6 |
|
大問11 |
|
| 大問2 |
水そうと水の出し入れ |
大問7 |
|
大問12 |
|
| 大問3 |
六角数と三角数 |
大問8 |
|
大問13 |
|
| 大問4 |
求積問題 |
大問9 |
|
大問14 |
|
| 大問5 |
規則性 |
大問10 |
|
大問15 |
|
| 問題解析 |
| 昨年に引き続き大問5題構成です。雙葉の算数といえば、問題のテーマ自体はオーソドックスであるものの計算処理が大変煩雑な印象があります。しかし、昨年に引き続き今年も解きやすい問題が並びました。大問2は解き方次第でやや面倒な処理を必要としますが、本校を目指して準備をしてきた受験生にとっては障害にはならない問題だったでしょう。今後の傾向については判断が難しいところです。繁雑な計算を要する問題が出題されても対応できるように準備しておきましょう。 |
理科
| 大問内容 |
| 大問1 |
食物連鎖 |
大問6 |
|
大問11 |
|
| 大問2 |
電力 |
大問7 |
|
大問12 |
|
| 大問3 |
酸化と還元 |
大問8 |
|
大問13 |
|
| 大問4 |
東京の地形 |
大問9 |
|
大問14 |
|
| 大問5 |
|
大問10 |
|
大問15 |
|
| 問題解析 |
| 大問4題、計算問題は途中式を書かせる形式となり、一昨年度までの出題形式に戻りました。問題の傾向はこれまで同様、思考力を問われる計算や記述問題が出題されました。大問2では、家庭用電源のブレーカーをテーマにした問題が出題されました。基本的な知識事項を確実なものにすると同時に、様々な事象に興味を持ち、調べたり考えたりすることを通して思考力を鍛えることが肝要です。 |
社会
| 大問内容 |
| 大問1 |
歴史(総合) |
大問6 |
|
大問11 |
|
| 大問2 |
地理(総合) |
大問7 |
|
大問12 |
|
| 大問3 |
公民(国内政治) |
大問8 |
|
大問13 |
|
| 大問4 |
|
大問9 |
|
大問14 |
|
| 大問5 |
|
大問10 |
|
大問15 |
|
| 問題解析 |
| 大問1は政治史を中心にした問題です。分量はもっとも多く、おそらく満点の半分程度を歴史分野が占めているようです。大問2の地理は新幹線の起点・終点を切り口にした問題です。知識問題が中心でした。そして大問3は国内政治からの出題です。国民主権と間接民主制に関する論述問題が出されていました。全体的に知識問題の多い学校ですが、求められる知識はかなりレベルの高いもの。参考書を隅々まで理解する必要がある学校です。 |